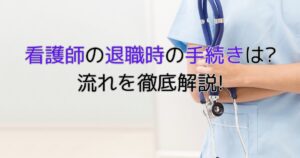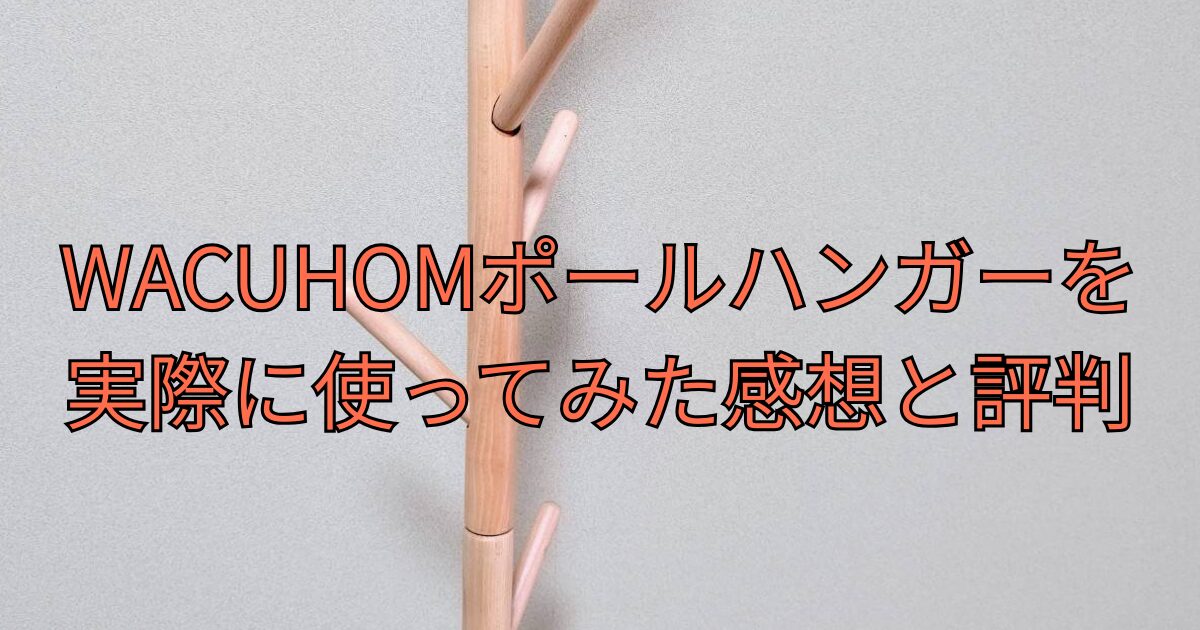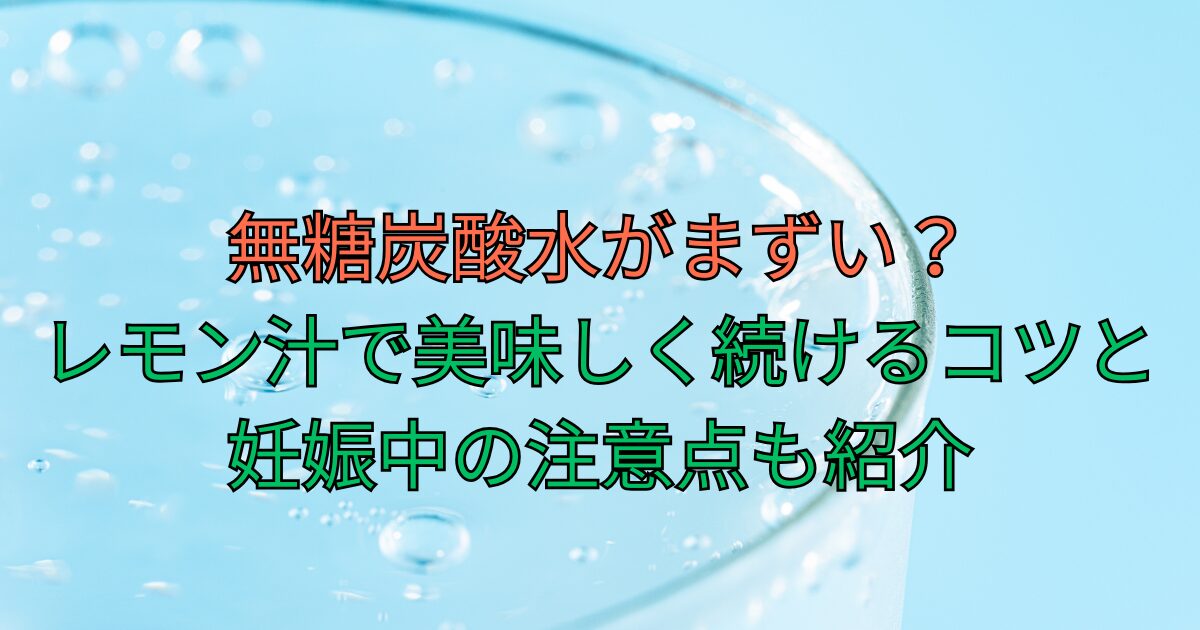退職したいけど、保険とかの手続きが心配だな。
看護師として退職した後、「健康保険はどうなるの?」「年金の手続きって必要?」「失業保険はもらえるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
退職後は少し気が緩むタイミングですが、保険や年金の手続きには期限があるため、早めに正しい知識を持って行動することが大切です。
- 看護師の退職後の手続き
- 健康保険・年金の切り替え
- 住民税の支払いついて
- 退職時に必要な書類一覧
- 失業保険の受給条件と申請の流れ
- 引っ越しや扶養変更がある場合の手続き
この記事では、看護師が退職後に行うべき主な手続きをわかりやすく解説します。
退職後の手続きを知ることで、不安を解消させましょう!
看護師の退職後、まず何から手続きすればいい
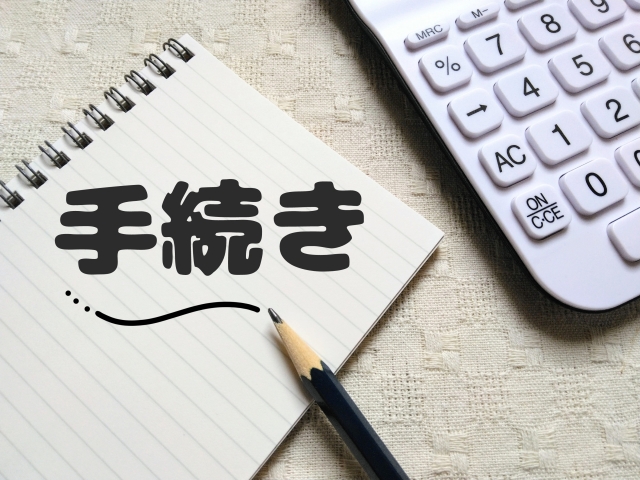
看護師として退職後に必要となる主な手続きは、以下の3つです。
- 健康保険の切り替え
- 年金の変更手続き
- 失業保険の申請(該当者のみ)
これらはそれぞれ期限や手続き場所が異なり、放置すると保険未加入や未納状態になってしまうこともあるため注意が必要です。
健康保険の切り替え
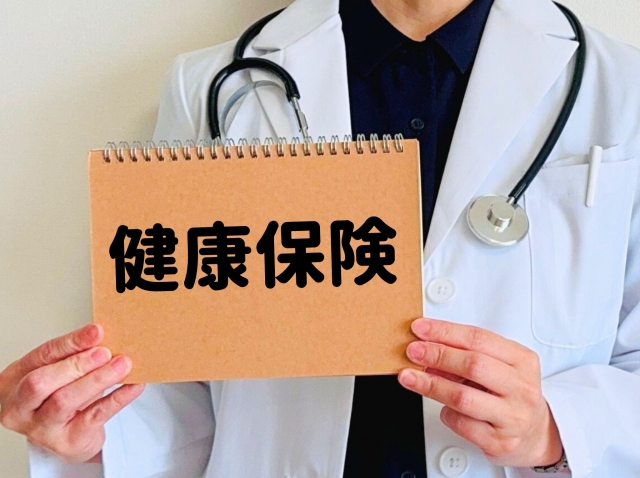
主な選択肢(任意継続・国民健康保険・転職先)
退職後の健康保険の切り替えは主に以下になります。
- 任意継続保険
- 国民健康保険
- 転職先の健康保険
任意継続保険とは?
会社員時代に加入していた健康保険を、退職後も最長2年間継続できる制度です。
加入には退職日から20日以内の申請が必要で、保険料は全額自己負担になります(会社が負担していた分も含まれます)。
前年の収入が高かった場合などは、国民健康保険より安くなる可能性もあります。
国民健康保険とは?
自営業者や退職者など、勤務先の保険に加入していない人が市区町村で加入する保険制度です。
保険料は前年の所得や世帯人数によって計算され、自治体により金額が異なります。
収入が少ない場合は減免制度が利用できることもあるため、市役所での相談がおすすめです。
転職先の健康保険とは?
次の勤務先が決まっている場合、その職場で新たに加入する健康保険を利用します。
入社日から自動的に加入となることが多く、特別な申請は必要ない場合もあります。
退職から1ヶ月前後の空白期間がある場合も、健康保険への加入は必須です。医療機関を利用した際に、未加入だと全額自己負担となるため、短期間でも適切な対応が必要です。
選択肢としては、以下のような方法があります。
- 一時的に任意継続保険を利用する
- 国民健康保険に短期間だけ加入する
期間の長さやライフスタイルに応じて、柔軟に選びましょう。
保険料の比較と実例
任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは人によって異なります。
- ✅ 高収入だった人:任意継続の方が安い可能性あり
- ✅ 収入が少ない/離職が長期にわたる人:国民健康保険の方が安くなる場合もあり
見積もりは、健康保険組合や市役所に相談しましょう。
私は任意継続保険と国民健康保険を比べたときに、任意継続保険が安かったです。
そのため、1年目は任意継続保険、収入が少なくなった2年目は国民健康保険に切り替えました。

正直想像以上に保険料がかかったので、どの保険にするかは、しっかり見積もりをしてもらうほうがよいです。
配偶者の扶養という選択肢
配偶者や親の健康保険に扶養として加入する選択肢もあります。
- 📌 年間収入130万円未満が条件
- 📌 保険組合ごとに基準が異なるため、事前確認が必要
健康保険は扶養に入っても、年金は別に手続きが必要です。
年金の切り替えと免除制度について
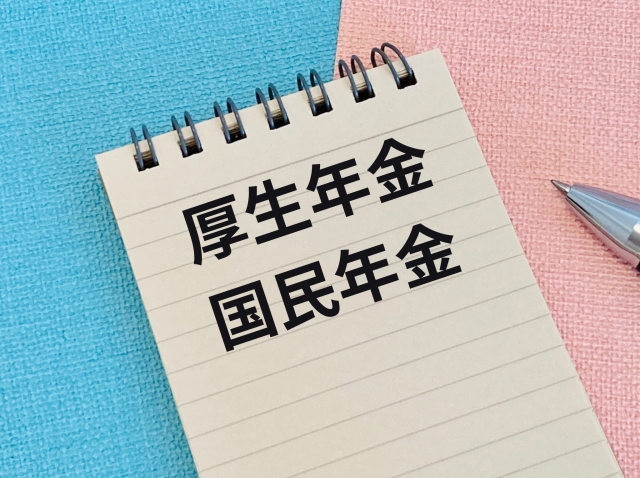
厚生年金と国民年金の違い
厚生年金は会社員や公務員が対象で、保険料は会社と本人で折半され、将来受け取る年金額も多くなります。
一方、国民年金は自営業者や無職の人が加入する制度で、保険料は全額自己負担となり、将来の年金額も比較的少なくなります。
そのため、退職後は厚生年金の資格を失い、自動的に国民年金に切り替える必要があります。
手続きは退職後14日以内に市区町村の役所で行います。
免除・猶予制度と実体験
保険料免除制度とは?
所得が一定以下の場合、国民年金の保険料が全額または一部免除される制度です。
将来の年金額は少し下がりますが、未納よりもはるかに有利です。
納付猶予制度の仕組み
50歳未満であれば、保険料の納付を猶予してもらえる制度があります。
猶予期間中は将来の年金額に影響しますが、あとから追納することも可能です。
どちらも市役所で申請可能ですので、退職後の収入が不安な方は早めに相談してみましょう。

私は退職後すぐに収入がなかったため、最初の1年は納付猶予制度を利用しました。数年後に追納し、年金額に反映されています。
住民税の支払いにも注意

退職後の生活費を考えるうえで、住民税の支払いも見落とせない要素です。
看護師として退職した後も、住民税の支払い義務は続きます。
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、たとえ退職して無職になっても支払う必要があります。
また退職前に再就職先が決まっている場合は、転職先の会社で給料から天引きされる方法もとれることがあります。
住民税の仕組みと支払い方法
通常、住民税は6月から翌年5月までの1年間を対象に課税されます。
会社員時代は給料から天引き「特別徴収」されていましたが、退職後は「普通徴収」となり、納付書で自分で支払う必要があります。
分割(年4回)か一括払いが選べます。
注意点と対策
退職月によっては、住民税の支払い方法が変わることがあります。
退職前に会社の経理部門に確認し、一括か普通徴収かを把握しておくと安心です。
さらに、退職後すぐに新年度(6月以降)の住民税が請求されるケースもあるため、資金準備が重要です。
所得の減少が見込まれる場合は、市区町村に相談することで減免や猶予を受けられる可能性があります。

退職後にいくら収入がなくても、住民税は請求されます。正直その金額に驚きましたし、税金関係で退職金も大幅に減りました。すぐに働かない場合は、税金用のお金も必ず確保しておきましょう。
退職時に必要な書類一覧

退職後の手続きでは、以下の書類が必要になる場面が多くあります。受け取り忘れのないよう、退職時に確認しましょう。
- 離職票(失業保険の手続きに必要)
- 源泉徴収票(確定申告や再就職時に使用)
- 健康保険資格喪失証明書(国民健康保険加入時に必要)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
特に「離職票」は、会社から自動で送付されない場合もあるため、忘れず依頼しておきましょう。
私は最初に離職票の大切さを知らず、結局の所失業保険を受け取りそこねました。

退職後にすぐに働き、失業保険を受け取る予定のない方は、離職票がなくても大丈夫です。また源泉徴収は再就職先の確定申告に必要なため、必ず保管しておきましょう。
失業保険の受給条件と申請の流れ

受給資格について
- 離職前2年間に、雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上あること
- 自己都合退職か会社都合退職かによって給付時期や日数が異なる
- 求職活動の意思と能力があること(ハローワークでの手続きが必要)
申請から給付までの流れ
- 退職後、ハローワークで「求職の申込み」と「離職票の提出」
- 認定日の説明を受け、初回認定日までに求職活動を実施
- 認定日に出向き、失業状態が認められれば給付開始
※ 自己都合退職の場合、給付までに2〜3ヶ月の「給付制限期間」が設けられることがあります。

会社の倒産などの「会社都合の退職」の場合は、すぐに失業保険を受け取ることができます。
引っ越しや扶養変更がある場合の手続き
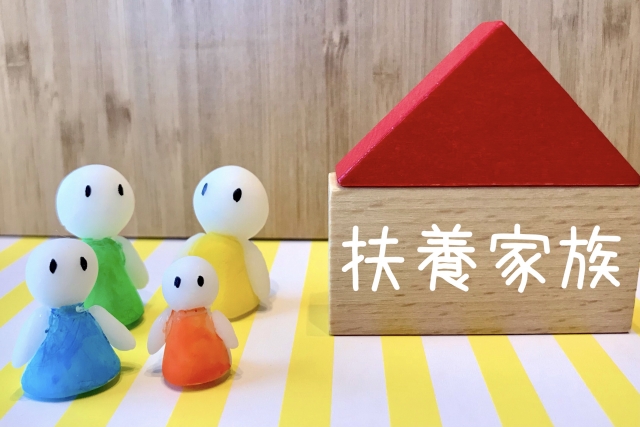
住所変更に伴う手続き
- 市区町村への転出届・転入届(14日以内)
- 国民健康保険・年金・住民税などの住所変更手続き
- 郵便物の転送設定(日本郵便の「転送届」)
扶養関係の変更
- 配偶者や子どもを扶養に入れていた場合、退職により保険証の再発行が必要
- 自身が扶養に入る場合(親・配偶者など)、勤務先の保険組合や市役所に申請
こんな方におすすめの記事です

退職後の手続きだけでなく、次のキャリアや退職前後の流れについても知りたい看護師さんにおすすめです。
まとめ

- 健康保険は「任意継続・国保・扶養・転職先」のいずれかを選ぶ
- 年金は国民年金へ切り替え、必要に応じて免除や猶予申請
- 住民税は前年収入に応じて請求されるため、準備が必要
- 離職票や源泉徴収票など、重要書類は必ず受け取る
- 失業保険の申請はハローワークで早めに
看護師の退職後には、健康保険・年金・住民税などさまざまな手続きが必要です。
特に保険や年金は申請期限が短く、対応が遅れると不利益を受ける可能性もあります。スムーズな退職後の生活を迎えましょう。
▼関連記事(ブログカード)
退職前の手続きがまだの方は、こちらの記事もチェック!
[看護師の退職時の手続きは?流れを徹底解説!]